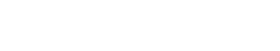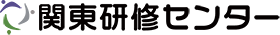介護講習KAIGO
- TOP >
- 介護講習
関東研修センターの介護講習
-

-
- 心地良い笑顔で挨拶ができる
- 謙虚な気持ちで相手と向き合えることができる
- 自分の意思・感情・考えをその場に応じた方法で伝達することができる
- 誠実に素直な心でおもてなしができる
- 相手に必要とされることを自分の喜びにすることができる
介護講習の資料をご希望の方はこちらにご入力ください








介護講習制度について
実習生の入国後は、実習生が配属先の施設などで実習が円滑に進むようになることを目的として、入国後講習が義務付けられています。
当センターの介護講習は介護に関する基本的な知識・実技修得のための介護講習42時間と、介護場面を意識した日本語講習を行っています。また、日本の文化の紹介や日本での生活習慣・ルール・マナーなどの指導にも力を入れています。
|
総合日本語/聴解/読解/文字/発音/会話/介護の日本語/作文 |
|---|---|
|
外部専門家を招いて実施 |
|
落ち着いた環境で体感型教育を実施 |
|
前述の環境で講義と演習を実施(以下詳細) |

介護導入講習42時間
カリキュラム(参考)

より実践的な介護導入講習と日本語
- 介護職が行うさまざまな業務内容について、「単純な仕事」「単なる作業」といった理解を避けるため、根拠や理由を説明し実際の生活場面の具体例を交えて演習を行います。
- 各国の文化について違いを確認しながら、日本の文化や慣習について、理解を深め、配属先施設における理念や方針について学び、実践にどのようにつなげるか考えます。
- サービス利用者の不安や困りごとに寄り添い、誠実に対応することは、実習生自身の仕事に対するやりがいや人生の価値を向上させるものと教授いたします。
- オリエンテーション
-
- 実習生一人ひとりの目的や目標について、自己紹介をかねて話し合い、講習修了後の自分のイメージを構築する。
- 居宅・通所・短期入所など、日本の高齢者施設、介護サービスに様々な種類があることを学ぶ。
- 介護職員の仕事内容(施設の1日の流れ、勤務体系)を再確認する。
- 介護の基本Ⅰ 3時間
-
- 介護の専門性(重度化防止の視点・利用者主体の基本姿勢・自立した生活を支えるための援助)に ついて理解する。
- 介護職として守るべきこと(社会的責任、プライバシーの保護・尊重)を理解する。
- 介護における安全の確保とリスクマネジメント(事故防止と安全対策)の必要性、事故発生時・利用者の急変時の対応について理解する。
- 介護職の健康管理の意義・目的と介護サービスの質について説明し、感染症予防と対策、手洗いの重要性・ポイント等について理解する。
- 科学的な根拠や理由(なぜその方法で行うのか)に基づく介護の実践と、利用者の個別性を尊重した支援を他職種と連携し、チームで行う必要性について理解する。
- 「個人として尊重されること」の大切さ、役割のある生活について学び、自立支援の目的、利用者「自己決定・自己選択」を促し尊重することの重要性を理解する。
- 介護の基本Ⅱ 3時間
-
- 人体の各部の名称と動きに関する基礎知識を学習する。
- 人はどのように老化していくのか、老化によって体や心はどのように変化するのか理解する。身体のしくみ(内臓等)を知り、高齢者に多い病気について学ぶ。また、前兆に気付くことで早期発見に繋げる。
- 老化に伴う心身の変化の特徴とその理解、老化に伴う喪失体験について学ぶ。
- 認知症に関する医学的な基礎知識の習得と認知症の人への援助・支援の基本や、身体障害の種類や内容について説明する。
- コミュニケーション技術 6時間
-
- 介護職が行うコミュニケーションを考え、人間的で効果的な基本的技法を理解する。
- 介護場面における基本的技法(傾聴・受容・共感、説明と同意)について学ぶ。
- それぞれの障害(視覚・聴覚・失語症・認知症)に応じた具体的技法について学ぶ。
- 介護におけるチームの情報伝達・共有(報告・連絡・相談)について学ぶ。
- 移動の介護 6時間
-

- 体位変換と移乗・移動の意義と目的について理解する。
- 移動・移乗に関連する用具の基本的な使用方法を理解する。
- 基本的な移動の介護(体位変換、移動(歩行、車いす移動等)を学び、実技を行う。
- 移動介助の留意点と事故予防について学び、安全面での配慮について考える。
- 食事の介護 6時間
-

- 食事の意義(生理的・心理的・社会的)目的等、食事の重要性について理解する。
- 利用者の食事の介護の一連の流れを通して、食事の介護を理解する。
- 基本的な飲み込み(摂食・嚥下)について、注意点について理解する。
- 利用者の自立支援のために介護職が行う内容や注意事項
(姿勢、食事の種類、誤嚥、窒息、準備、配膳、福祉用具)について理解する。 - 事故はどのような場所でどのような時に起こりやすいか、予防と対策を学ぶ。
- 排泄の介護 6時間
-

- 排泄の意義と目的を学び、自尊心への十分な配慮が必要であることを理解する。
- 基本的な排泄の介護(ポータブルトイレ、便器・尿器、おむつ等)の実技を行う。
- 排泄介助の留意点と事故予防について学び、利用者の状態・状況に応じた介助を行うことを理解する。
- 衣服の着脱 6時間
-

- 身じたくの種類(衣服の着脱、洗面、整髪、爪切り、ひげそり、化粧)と、意義と目的について理解する。
- 準備から着脱までの一連の流れを通して、基本的な着脱の介護を理解する。
- 可動域に配慮した身体の動き等、着脱介助の留意点と事故予防を理解する。
- 入浴・身体の清潔 6時間
-

- 入浴・身体の清潔の意義と目的、体の清潔を保つことの重要性を理解する。
- 基本的な入浴の介護(特殊浴槽、チェアー浴、一般浴槽等)を理解する。
- 入浴以外の 身体清潔の方法(足浴・手浴、身体清拭)を理解する。
- 褥瘡の主な原因・できやすい部位と予防法について、理解する。
- 入浴・身体清潔の留意点と事故予防について理解する。
(羞恥心の配慮・湯温・シャワーのかけ方・体や頭の洗い方、道具の説明、ヒートショック、ドライヤーの使用方法、水分補給等)